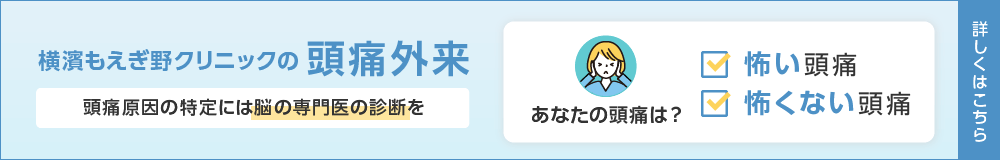脳梗塞について

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで脳に血液が流れなくなり、脳の細胞が死んでしまう病気です。突然、半身の手足の麻痺やしびれ、ろれつが回らない、言葉が出ない、視野が欠ける、めまい、意識障害などの症状が現れることが多く、重い後遺症が残ることがあります。
脳梗塞の原因は様々ですが、主なものとしては高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動などの生活習慣病や、動脈硬化が挙げられます。また、喫煙や多量の飲酒、運動不足、脱水などもリスクを高めます。
脳梗塞の治療は、発症からの時間経過によって大きく異なります。超急性期(発症後4~5時間以内)であれば、血栓を溶かす薬の点滴や、カテーテルを使った血管内治療で血流を再開させることを目指します。発症から時間が経過している場合は、点滴や内服薬で脳の保護や再発予防を行います。
脳梗塞の後遺症は、麻痺や言語障害、感覚障害、高次機能障害など多岐にわたります。そのため、急性期治療だけでなく、リハビリテーションも非常に重要になります。
もし、ご自身や周りの方に上記の症状が見られた場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。一刻も早い治療が、後遺症を最小限に抑えるために最も重要です。
症状
脳梗塞の症状は、多くの場合、突然現れることが特徴です。以下の症状が一つでも現れた場合は、すぐに救急車を呼ぶことをためらわないでください。
運動麻痺
片側の手足の麻痺: 突然、片方の腕や脚に力が入らなくなる、持ち上げられない、動かしにくいといった症状が現れます。箸が持ちにくい、ボタンがかけにくい、歩きにくい、つまずきやすいなどの形で気づくこともあります。
顔面麻痺: 口角が下がる、まぶたが閉じにくいなど、顔の片側が動かしにくくなることがあります。笑うと左右非対称になることがあります。
感覚障害
片側の手足や顔のしびれ: 突然、片方の手足や顔の感覚が鈍くなる、ピリピリする、触られている感じがしないといった症状が現れます。
異常な感覚: 触れていないのにチクチクする、熱い、冷たいといった異常な感覚が生じることがあります。
言語障害
ろれつが回らない(構音障害 ): 言葉がはっきりしない、不明瞭になることがあります。
言葉が出てこない、理解できない(失語症): 言いたい言葉が出てこない、人の言っていることが理解できない、言葉を間違って使うなどの症状が現れます。
視覚障害
片方の目が見えにくい、見えない(一過性黒内障): 突然、片方の目が一時的に見えなくなることがあります。これは脳梗塞の前兆である可能性もあります。
視野の半分が欠ける(半盲): 左右どちらかの視野の半分が見えなくなることがあります。
物が二重に見える(複視): 物が重なって見えることがあります。
バランスの障害
ふらつく、めまいがする、足元がフワフワするなど
原因
 脳梗塞の主な原因は、脳に血液を送る血管が詰まることによって起こる虚血性脳梗塞です。血管の詰まりは血のかたまりである血栓ができることで発症します。これは、脳梗塞全体の約8割を占めます。
脳梗塞の主な原因は、脳に血液を送る血管が詰まることによって起こる虚血性脳梗塞です。血管の詰まりは血のかたまりである血栓ができることで発症します。これは、脳梗塞全体の約8割を占めます。
虚血性脳梗塞の原因
アテローム性動脈硬化症
動脈の内壁にプラーク(コレステロールや脂肪などが蓄積した塊)ができ、血管が狭くなったり、プラークが剥がれて血栓となり血管を塞いだりします。
心原性脳塞栓症
心臓でできた血栓が血流に乗って脳の血管に流れ込み、血管を塞ぎます。心房細動などの不整脈が原因となることが多いです。
ラクナ梗塞
脳の細い血管が詰まることで起こります。高血圧が主な原因となります。
また、血管が破れて出血することで起こる出血性脳梗塞(脳出血、くも膜下出血)もありますが、これは脳梗塞全体の約2割です。
脳梗塞リスクを高める要因
- 高血圧
- 糖尿病
- 脂質異常症(高コレステロール血症など)
- 心房細動などの不整脈
- 喫煙
- 肥満
- 運動不足
- 過度の飲酒
- 加齢
- 脳梗塞の既往歴
- 家族歴
治療
脳梗塞の治療は、発症からの時間経過や病型によって大きく異なります。
主な目的は以下の通りです。
・詰まった血管を再開通させ、脳への血流を回復させること(虚血性脳梗塞の場合)
・出血を止めること、または脳の腫れを抑えること(出血性脳梗塞の場合)
・脳のダメージを最小限に抑えること
・合併症を予防すること
・再発を予防すること
虚血性脳梗塞の治療
発症後、できるだけ早く治療を開始することが重要です。時間経過とともに脳細胞は死滅してしまうため、「時間との勝負」と言われます。
超急性期治療(発症後数時間以内)
血栓溶解療法(t-PA静注療法):
詰まった血管を溶かす薬(t-PA)を静脈から投与します。発症後2~3時間以内に行うことが推奨されています。ただし、出血のリスクなどから適応には厳格な条件があります。
血管内治療(脳血管内カテーテル治療):
カテーテルという細い管を足の付け根などの血管から脳の血管まで挿入し、血栓を回収したり、血管を広げたりする治療法です。発症後、血栓溶解療法の適応がない場合や効果が不十分な場合、または特定の部位の太い血管が詰まっている場合などに検討されます。時間制限はありますが、近年適応が拡大しています。
急性期治療(発症後数日以内)
抗血小板薬、抗凝固薬の投与: 血栓が再びできるのを防ぐために、アスピリンやクロピドグレルなどの抗血小板薬や、ヘパリンやワーファリン、直接経口抗凝固薬(DOAC)などの抗凝固薬が投与されます。
脳保護薬の投与:
脳細胞の保護や浮腫の軽減を目的とした薬剤が投与されることがあります。ただし、明確な効果が証明されている薬は限られています。
合併症の予防と管理:
肺炎、褥瘡、深部静脈血栓症などの合併症を予防するための対策や、起こってしまった場合の治療が行われます。
リハビリテーションの開始:
早期からリハビリテーションを開始し、機能回復を目指します。
慢性期治療・再発予防
生活習慣の改善:
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの管理、禁煙、節酒、適切な食事、適度な運動などが重要です。
薬物療法:
抗血小板薬や抗凝固薬による再発予防、高血圧や脂質異常症などの基礎疾患の治療薬が継続されます。
定期的な検査:
脳の状態や基礎疾患の管理のために、定期的な画像検査や血液検査などが行われます。
出血性脳梗塞の治療(脳出血、くも膜下出血):
出血性脳梗塞の治療は、出血の原因や部位、量、患者さんの状態によって大きく異なります。
脳出血の治療
保存的治療:
出血量が少ない場合や、手術が困難な部位の場合などに行われます。安静、血圧管理、脳圧を下げるための薬(浸透圧利尿薬など)の投与、止血薬の投与などが行われます。
外科的治療:
出血量が多い場合や、脳ヘルニア(脳が圧迫されて移動してしまう状態)の兆候がある場合などには、血腫を取り除く手術が行われることがあります。
くも膜下出血の治療
原因となった血管病変の治療: 脳動脈瘤が原因の場合には、再破裂を防ぐために手術(クリッピング術や血管内塞栓術)が行われます。脳血管攣縮の予防と治療: くも膜下出血後に起こりやすい血管攣縮(血管が収縮して血流が悪くなること)を予防したり、起こってしまった場合に血管拡張薬などを用いて治療したりします。
水頭症の治療:
髄液の流れが悪くなり、脳室に髄液が溜まってしまう水頭症が起こることがあり、その場合には髄液を排出するための手術(脳室ドレナージ術やシャント術)が行われることがあります。
全身管理:
呼吸管理、血圧管理、電解質バランスの調整など、全身状態の管理が重要になります。
出血性脳梗塞の場合も、急性期からリハビリテーションを開始し、機能回復を目指します。また、再出血を予防するための治療や、後遺症に対する治療も継続的に行われます。
脳梗塞の治療は、非常に専門的な知識と迅速な対応が求められます。疑わしい症状が現れた場合は、ためらわずに救急車を呼ぶことが重要です。また、日頃から生活習慣に注意し、リスク要因を管理することが、脳梗塞の予防につながります。
リハビリ
脳梗塞のリハビリは、失われた機能の回復と日常生活への復帰を目指す重要な過程です。発症直後の急性期から始まり、回復期、生活期へと段階的に進みます。
急性期では、関節の拘縮予防や呼吸訓練など、早期離床に向けたリハビリが行われます。状態が安定するにつれて、回復期では専門病院などで集中的な訓練が行われます。理学療法では、歩行やバランス、筋力などの運動機能回復を目指し、作業療法では、食事や着替えといった日常生活動作の再獲得、高次脳機能障害へのアプローチなどが行われます。言語聴覚療法では、言葉や飲み込みの訓練を通して、コミュニケーション能力や食生活の改善を図ります。
退院後の生活期では、自宅や通所リハビリなどを利用し、維持・改善を目指します。自主トレーニングの指導や、社会参加への支援も重要です。
リハビリは、医師、セラピスト、看護師、ソーシャルワーカーなどが連携し、患者さん一人ひとりの状態や目標に合わせた個別プログラムで行われます。早期からの適切な介入と、患者さん自身の意欲、そして周囲のサポートが、より良い回復への鍵となります。諦めずに継続することが大切です。
予防法
脳梗塞を予防するためには、以下の点が重要です。
生活習慣病の予防と管理
高血圧の管理:
定期的な血圧測定を行い、医師の指示に従って適切な治療を受けましょう。減塩を心がけた食生活も重要です。
糖尿病の管理:
血糖値をコントロールするために、食事療法、運動療法、薬物療法を適切に行いましょう。
脂質異常症の管理:
コレステロールや中性脂肪が高い場合は、食事療法や薬物療法で適切な管理を行いましょう。
禁煙:
喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を促進する最大の危険因子です。禁煙することが最も重要です。
節酒:
過度の飲酒は血圧を上昇させる可能性があります。適量を守りましょう。
肥満の解消:
バランスの取れた食事と適度な運動で、適切な体重を維持しましょう。
適度な運動:
ウォーキングなどの有酸素運動を習慣にしましょう。
健康的な食事: 塩分、脂肪分を控え、野菜や果物を積極的に摂りましょう。
その他の注意点
心房細動の治療:
心房細動は心原性脳塞栓症の大きな原因となります。早期に発見し、医師の指示に従って適切な治療を行いましょう。
脱水予防:
こまめに水分補給をしましょう。
ストレス管理:
ストレスは血圧上昇の原因となることがあります。適度な休息や趣味などでストレスを解消しましょう。
定期的な健康診断:
定期的に健康診断を受け、血圧、血糖値、脂質などをチェックしましょう。脳ドックも有効な場合があります。
寒暖差に注意:
冬場の急な温度変化は血管を収縮させ、血圧を上昇させる可能性があります。暖房器具などを活用し、温度変化を緩やかにしましょう。
これらの予防法を実践することで、脳梗塞のリスクを大幅に減らすことができます。特に生活習慣病の予防と管理は非常に重要です。